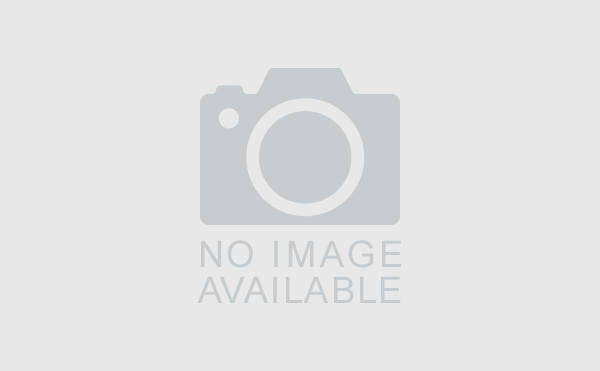足場とは?種類・特徴・メリットを徹底解説
建築現場や外壁工事で見かける「足場」とは、高所での作業を安全かつ効率的に行うために組み立てる仮設構造物です。職人が安心して作業できる安定した作業床を確保し、工具や資材を運ぶ通路にもなるため、足場は工事に欠かせない存在です。本記事では、足場の種類や特徴、メリット・デメリットを階層ごとに整理して解説します。検索で多くの方が疑問に思う「枠組み足場と単管足場の違い」や「くさび足場とビケ足場の違い」といった関連キーワードにも触れていますので、足場選びの参考にしてください。

足場の種類と基本構造
足場は大きく枠組み足場・くさび足場・単管足場・吊り足場の4種類に分けられます。それぞれ構造や部材、組み立て方法が異なり、用途や適用高さも変わります。以下では各種類とそのサブカテゴリーについて詳しく紹介します。
枠組み足場

枠組み足場は、ビルや中高層マンションの外壁工事をはじめ、工場・土木工事や橋脚など幅広い現場で使用される足場です。門形に溶接された鋼管の枠(建枠)と手すり、筋交い、布板(作業床)などをピンやクランプで連結して組み立てます。規格化された枠材を用いるため部材数が少なく、短時間で広い面積を組み上げられるのが特徴です。安全性の高さから公共工事や高層建物に多く用いられています。旧JIS基準では高さ45mまでを目安に設計されることが多く、それ以上の高さでは補強や仮設計算が必要とされます。
門型枠組み足場
門型枠組み足場は、「ビティ足場」とも呼ばれ、門形に溶接された建枠を縦横に連結して組み立てるオーソドックスな枠組み足場です。 高さ45mまで補強なしで組み立てられるとされており(例外を除く)、高層用足場として長年使われてきました。建枠のサイズが固定されているため建物の高さが均一でないと組み立てが難しい場合があり、枠が大きく重量もあるため資材置き場や搬入経路の確保が必要です。2010年代半ば~後半(2015年頃)からは安全性と作業効率を両立した次世代足場の登場により新設現場での採用は減少傾向ですが、リース市場では依然多く流通しています。
H型枠組み足場
H型枠組み足場は、建枠の横桟がH形状になっており、手すり先行工法に対応した枠組み足場です。組み立て時に上段の建枠を先行して設置し、手すりを付けてから作業床を敷くため墜落リスクを低減できます。公共工事やマンション・高層ビルの新築工事では安全性が重視されるためH型の採用が増えています。門型と同様に枠材が大きく保管スペースが必要ですが、手すりが先に設置できるので作業者の心理的負担が少なく、法令や元請けの安全要求に応えやすいのがメリットです。
くさび足場

くさび足場は、支柱と手すり、布板を楔(くさび)で緊結する足場です。支柱に溶接された金具に手すりや筋交いを差し込み、ハンマーで打ち込んで固定するため、部材点数が少なく組み立て・解体がスピーディーに行えます。凹凸のある敷地や寸法誤差の大きい現場でも融通が利き、戸建住宅や中低層建築で広く採用されています。従来型は低層用が中心ですが、最近はロック機構や手すり先行工法を採用した次世代足場が登場し、より高層の現場に対応できる製品もあります。
次世代足場(くさび式)
近年登場した次世代足場は、従来のくさび足場を改良し、手すり先行工法や落下防止機能を標準化したシステム足場です。支柱や手すりにロック機構が付いており楔が外れにくい構造になっているため安全性が高いのが特徴です。また部材をコンパクトに収納できるよう設計され運搬効率も向上しています。製品によっては枠組み足場並みの高層用に対応し、枠組み足場の代替として採用される現場も増えています。代表的な製品には「アルバトロス」「ダーウィン」「IQ」などがあり、各社が特徴の異なるラインアップを提供しています。
従来型くさび足場(ビケ足場)
従来型のくさび足場は、「ビケ足場」や「キャッチャー足場」など商品名で呼ばれることもあります。支柱の高さや手すりの長さが一定でない現場でも柔軟に調整できるため、主に戸建住宅や低層アパートの外壁・屋根工事に多用されています。高層建物では概ね30m前後までが使用目安とされ、それ以上の高さで使用する場合は補強や仮設計算が必要です。組み立てが容易でコストも比較的安い一方、手すりや布板の設置順序を誤ると墜落リスクが高まるため、資格を持った作業主任者の指導のもとで正しく組み立てることが重要です。
単管足場
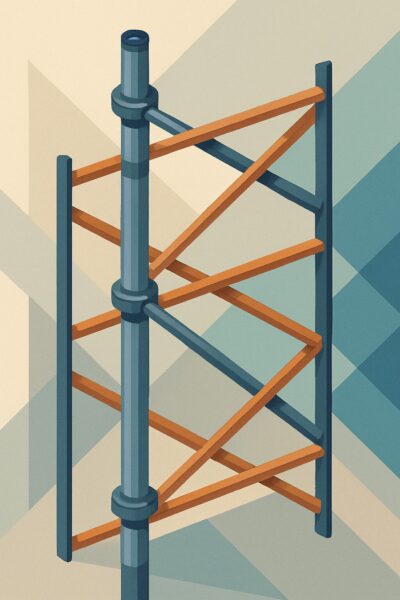
単管足場は、直径48.6㎜の鋼管(単管)とクランプを用いて支柱や手すりを組み立てる足場です。パイプとクランプを自由に配置できるため、ビルやマンション、工場、橋梁やプラント設備など複雑な形状の建物や狭いスペースにも設置しやすいのが特徴です。一方で部材数が多く作業者の熟練が求められるほか、組み立てに時間がかかるというデメリットがあります。単管足場の安全な作業高さは概ね31m程度までとされ、それ以上の高さでは仮設計算や補強が必要です。
単管本足場
単管本足場は、建物の外側に支柱を立てて作業床を設ける一般的な単管足場です。枠組み足場やくさび足場では対応しにくい半端な寸法や複雑な形状を調整できるため、戸建住宅から店舗改修、橋脚工事などさまざまな用途で利用されます。支柱間の幅や高さを現場に合わせて自由に設定できる反面、単管やクランプを一つひとつ組み合わせる手間がかかり、作業者には一定の技能が求められます。
単管一足足場(ブラケット足場・抱き足場)
ブラケット足場は、縦柱にブラケット(片足支持金具)を取り付け、その上に足場板や布板を渡して作業床を構築する足場です。一方、抱き足場は縦柱に3連クランプを使用して布パイプを縦柱の両側に渡す構造で、建物と足場の間隔が20〜30センチほどしかない極狭地でも設置できるのが特長です。どちらの工法も狭い場所で活用できますが、支持点が少なく高さに制限があり、安全帯や張出し支持具の併用など十分な安全対策が求められます。
吊り足場

吊り足場は、上部構造から支柱やチェーンで作業床を吊り下げる足場で、橋梁やプラント設備の下部工事、大きな吹き抜けなど地面から支える足場が設置できない場所で使用されます。地上に支柱を立てないため、下部のスペースが確保できない場合でも安全な作業床を提供できます。吊り足場には以下の2種類があります。
チェーン・パイプ吊り足場
吊りチェーンや吊りパイプで親パイプを吊り、その上にころばしパイプ(水平パイプ)を渡して足場板を敷く工法です。部材点数が少なく比較的安価で、橋桁や水管橋など線状構造物の補修工事でよく使われます。吊り下げる支点や資材の荷重設計を厳密に行い、安全帯の使用や荷揚げ・荷降ろし手順を徹底することが重要です。
パネル式吊り足場
パネル式吊り足場は、親パイプやころばしパイプ、床材、落下防止ネットを一体化したパネルユニットをチェーンで吊り下げて連結し、広い作業床を構築する工法です。ユニット化されているため部材点数が少なく、架設・解体が迅速に行えるのが特長で、支柱を立てられない橋梁下面やプラント設備の下部などで活用されています。
パネルは連結済みの足場の上から順次取り付けていくため常に安定した作業床が確保され、単管パイプで組む従来の吊り工法に比べて安全性が高いと評価されています。パネルは進行方向に66cmピッチで繋げられるモジュール設計で、幅は2m・3m・3.85mの3種類、床材はアルミ縞板・耐水コンパネ・エキスパンドメタルの3タイプから選べます。
パネル同士を内蔵ジョイントで確実に連結することで安定した作業床を形成し、支える吊りチェーンは重量を受け持ちますが、パネルが安定するのはジョイント連結によるため未連結のパネルには決して乗らないことが重要です。
また、高い位置に簡単に安全帯フックを掛けられる構造を備えていますが、作業時は必ず安全帯を2丁掛けで使用し、最初と最後のパネルは4点吊りとフレ止め処置を行うなど、マニュアルに従った正しい手順を守って安全に作業を進める必要があります。
足場の比較表 – 用途・高さ・特徴
※この表は左右にスクロールできます
| 種類 | 主な用途・現場 | 目安高さ | 特長 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|---|
| 枠組み足場(門型) | ビル、中高層マンション、工場、土木工事、橋脚 | ~45m | 門形の枠を連結するオーソドックスな枠組み足場 | 施工スピードが速い 高い剛性 |
部材が大きく保管スペースが必要 高さが揃っていないと組みにくい |
| 枠組み足場(H型) | マンション、公共工事、高層ビル | ~45m | 手すり先行工法に対応したH形枠 | 安全性が高い 法令に対応しやすい |
部材が大きく重量がある |
| 次世代足場(くさび式) | ビル、中高層マンション、公共工事、工場 | ~45m(製品による) | ロック機構付きくさび足場 | 落下防止機能が標準装備 部材がコンパクト |
導入コストが高い 専用部材が必要 |
| 従来型くさび足場 | 低層住宅、改修工事 | 低層 | 支柱に楔で固定する足場 | 組み立てが速い 凹凸のある敷地でも対応 |
中層以上では補強が必要 手すり先行ではない |
| 単管足場 | ビル、マンション、工場、橋脚・橋梁、プラント設備 | ~31m程度 | 単管とクランプを自由に配置 | 狭い場所や複雑な形状に対応 寸法調整が容易 |
組み立てに時間と熟練が必要 |
| 単管一足(ブラケット)足場 | 狭小地、極狭地 | 低層 | ブラケットや抱き足場で壁面に固定して作業床を作る | 狭い箇所にも設置可能 | 支持点が少なく高さに制限がある |
| 吊り足場(パイプ・チェーン) | 橋梁、ダム、プラント設備 | 支点に依存 | 上部から吊り下げて作業床を構築 | 地上スペースが不要/連続した長さを確保 | 吊り元の強度確保が必須/熟練した経験と技術が必要 |
| 吊り足場(パネル式) | 橋梁、プラント設備 | 支点に依存 | SKパネルなどのパネルを吊り下げ連結して作業床を構築 | 広い面積を効率よく設置/落下防止機能付き | 専用パネルが必要/材料の重量が重い |
関連サービス・おすすめページ
足場の種類や計算方法についてさらに理解を深めたい方のために、当サイト内の関連ページやツールをまとめました。どれも無料で利用できるので、ぜひ活用してみてください。
- 架け郎(くさび足場版)・ASIBA+ – 足場計算アプリ – スパン数や段数を入力するだけで、くさび式や次世代足場の必要部材や平米数を自動で計算できる無料ツールです。
- 足場積載荷重の計算方法 – 足場の種類ごとに許容積載荷重や安全基準をまとめた解説記事で、適正な荷重管理の重要性を学べます。
- 足場面積の正確な計算方法 – 外周と高さから足場面積を求める手順や単価の目安を紹介し、計算アプリとの連携方法も解説した記事です。
- 足場使用規制の全面強化についての解説 – 改正労働安全衛生規則によって足場の幅や建物との間隔などが厳格化されたポイントを整理した記事です。
- ニュース一覧 – 当社の最新情報やアップデートをまとめて掲載しています。
よくある質問と関連キーワードの解説
最後に、読者から寄せられることの多い疑問に回答します。
枠組み足場と単管足場の違いは?
大きな違いは構造と施工スピードです。枠組み足場は規格化された建枠・手すり・筋交いを組み合わせるため部材点数が少なく、短時間で組み立てられます。一方、単管足場はパイプとクランプを自由に配置できるので複雑な形状にも対応できますが、部材が多く組立時間がかかり、熟練の技術が必要です。高さの制限も異なり、枠組み足場の一般的な目安は45m程度、単管足場は31m程度とされています。
くさび足場とビケ足場の違いは?
ビケ足場は長谷川工業が販売するくさび式足場の登録商標ですが、一般的には従来型のくさび足場全体を指す場合があります。基本構造はどちらも支柱に金具を差し込み、楔をハンマーで打ち込んで固定する点で同じです。ただし、最近は各メーカーが独自の改良を加えた次世代足場を販売しており、手すり先行工法や軽量化などの付加価値が異なるため、製品選定時には用途や安全機能を確認すると良いでしょう。
枠組み足場やくさび足場の標準寸法は?
枠組み足場の建枠幅は一般に914mmと1,219mmが標準となっています。高さは1,725mmが標準で、複数のサイズを組み合わせて建物の高さに対応します。くさび足場の支柱ピッチは600mm、900mm、1,200mmなどの規格があり、手すりの長さや布板の幅もメーカーによって複数の寸法が用意されています。単管足場はパイプを自由に配置できるため、幅や高さは現場に応じて調整します。
枠組み足場やくさび足場の組み方は?
枠組み足場では、まず敷板を敷きその上にジャッキベースの高さを水平に設置し、建枠を立てて交差筋交いで固定します。その後、布板を掛けて階段を取り付けて上層へと作業を進めます。くさび足場では、まず敷板を敷きその上にジャッキベースの高さを水平に設置し、支柱を立て、手すりや筋交い、布材を楔で打ち込んで固定し、最後に布板を敷きます。いずれも手すりを先に取り付ける「手すり先行工法」が推奨され、安全帯や墜落制止用器具の使用が義務付けられています。
足場の図面や計画書は必要?
高さ10m以上で使用期間が60日を超える工事や、吊り足場など特殊な足場を設置する場合は、労働安全衛生法の規定により「足場の設置届」を労働基準監督署に提出する必要があります。その際、足場の配置図や計画書が求められます。届出が不要な工事でも、施工中の安全を確保するために足場計画書を作成し、使用者全員で共有することが望ましいです。
次世代足場の種類やデメリットは?
次世代足場には、アルバトロス、ダーウィン、IQなど複数のブランドがあり、手すり先行機構や軽量化、部材のコンパクト化などの特徴があります。一方で、導入コストが高く、従来の足場より部材単価が高いこと、従来型との互換性がない場合があることがデメリットとして挙げられます。導入を検討する際は、工事規模やリース会社の在庫状況、作業者の習熟度を考慮しましょう。
くさび足場と枠組み足場の違いは?
くさび足場は楔をハンマーで打ち込んで部材を固定するため、部材点数が少なく小規模・中規模工事に適しています。凹凸のある地面や寸法誤差の大きい建物でも、楔のピッチに合わせて高さを調整しやすいのがメリットです。枠組み足場は門形の建枠を連結するため高い剛性を確保でき、施工スピードが速く、中高層ビルや公共工事に向いています。用途や現場条件に応じて使い分けましょう。
くさび足場の組み方や単価は?
くさび足場は支柱に専用金具を差し込み、楔をハンマーで打ち込んで固定します。組立は上方向へ順に行い、手すりを先に設置することで安全が確保されます。単価は地域や物件の規模によって異なりますが、一般的な住宅用では1平方メートルあたり数百円程度が相場です。次世代足場や特殊部材を使用する場合は単価が上がるため、複数社から見積もりを取って比較することをおすすめします。
まとめ
足場は建築工事の安全と効率を支える重要な仮設構造物であり、現場条件や工事内容によって最適な種類が異なります。枠組み足場やくさび足場、単管足場、吊り足場といったそれぞれの特徴とメリット・デメリットを理解することで、工事の安全性を高め、コストや工程の最適化につながります。本ページでは「足場とは何か」という基本から各種類の違い、関連キーワードの疑問まで網羅しました。足場に関する計画や見積もり、資格について詳しく知りたい方は、他の記事や専門家への相談も併せて参考にしてください。