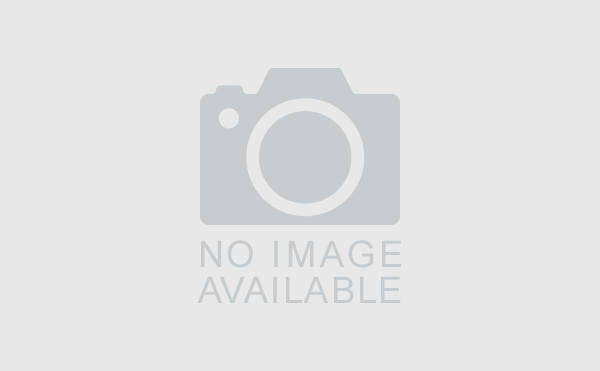足場仕事とは?安全な足場の重要性・種類・組立て手順・解体のポイントを徹底解説
建設・リフォーム現場では、高所での作業が必須です。しかし手が届かない場所に無理やり手を伸ばすと作業効率が低下し、墜落の危険も高まります。そこで頼りになるのが足場仕事です。足場を設置することで、高所でも安全かつ効率的に作業ができるようになります。このページでは、足場の種類や組立て手順、解体のポイントに加え、労働安全衛生規則や資格など法的な要求も含めて詳しく解説します。検索意図に応える関連ページへのリンクも用意しているので、ぜひ参考にしてください。
足場仕事の概要と重要性

足場とは
足場とは、建物や工作物の外側に組み上げる仮設構造物です。主な目的は次の二つです。
- 高所へのアクセスの確保 –
足場を使うことで、建物の高い部分や手が届かない場所に安全に到達できます。外壁塗装や屋根工事、解体工事など多くの場面で必要になります。 - 作業効率の向上 –
安定した作業床があることで、道具や材料を置きながら作業できるため効率が上がります。
安全な足場を設置することで、労働者の墜落・転落事故を防ぐだけでなく、周囲へ落下物を発生させないという意味でも社会的責任を果たせます。労働安全衛生規則では足場に関する詳細な規定を設けており、事業者には法令遵守が求められます。
足場の主な種類と特徴

足場には現場に応じたさまざまな工法があります。ここでは一般的な種類と特徴をまとめます。
| 種類 | 特徴・メリット | 留意点 |
|---|---|---|
| 枠組み足場 | 鋼製のフレームに交差筋交いを組み合わせる定番の足場。部材が軽く丈夫で高層(45 mを超えると補強が必要)にも対応できます。 | 部材の種類が豊富でさまざまな用途で利用可能、狭い場所には不向き。 |
| くさび式足場 | 支柱の接合部にくさび(楔)を打ち込んで固定するタイプ。ハンマーで叩くだけで組立てや解体ができ、スピーディーに構築できます。 | 低層用の足場なので高層には不向き。狭い場所には不向き。 |
| 次世代足場 | 手すりを先行して取り付ける先行手すり工法(手すり先行工法)を採用した次世代の足場。作業床を組む前に外側手すりを先に取り付けるため、墜落リスクが低く心理的負担も減少します。くさび式足場の様に接合部に楔を打ち込んで固定します。 | 後述する手すり先行工法の規定に従う必要があります。 |
| 張出し(張り出し)足場 | 建物の壁面から張り出す梁を用いて作業床を設置する工法。地面や道路スペースが確保できない場合に適しています。 | 梁の強度計算や固定方法を誤ると危険が高まります。 |
| 単管足場 | 直径48.6 mmの鋼管をクランプで連結して作る柔軟な足場。狭い場所や複雑な形状の建物に適しています。 | 熟練した技術が必要で、部材数が多いので組立てに時間がかかります。 |
| 吊り足場 | 橋梁や高架下などで使用される、上部から単管パイプやチェーンで吊り下げた作業床。地面の状況に左右されず高所作業が可能です。 | 吊り装置の安全確保が重要で、強風などの影響を受けやすい。 熟練した職人による墜落・落下措置を確実に行わないと危険。 |
| 移動式足場(ローリングタワー) | キャスター付きの小型タワーで、軽作業や屋内工事などでよく利用され簡単に移動することができます。 | キャスターの耐荷重や横幅に比べて高さがあるため、傾斜した地面では転倒のリスクがあり、アウトリガーなどでしっかり固定する必要があります。さらに、高さには制限があり、一般的にはビル2〜3階程度の高さまでの作業に用いられるとされています。積載荷重を守り、人が乗ったまま移動させないなど安全な使用が求められます |
足場は現場の条件に合わせて適切な種類を選ぶ必要があります。特に近年は労働災害防止の観点から安全性の高い次世代足場(手すり先行工法を採用した足場)が普及しており、国のガイドラインでも推奨されています。
次世代足場の見積もりや計算は「ASIBA+」アプリが便利です。
足場の安全な組立て:基礎から手すりまで
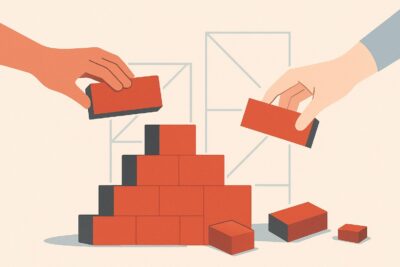
足場を組み立てる作業は、基礎準備から手すりの設置まで一連の手順を計画的に行う必要があります。以下では枠組み足場を例に、一般的な組立て手順を解説します。
1. 設置計画と基礎準備
まずは足場の設置計画を立て、施工図や周辺環境を確認します。労働安全衛生規則では、足場材料は破損や腐食に加え、変形や曲がり、割れなどの欠点がないものを使用しなければならないと規定しています。木材の場合も割れや腐朽のない部材を選定し、節目や大きな節があるものは避けましょう。
基礎部分では地面を平坦に整地し、敷板や角材を敷いた上にジャッキベースを設置します。支柱を受けるベース金具は四隅の穴を2本以上の釘で敷板に固定し、滑動を防止します。さらに、脚部のできるだけ低い位置に根がらみを設置して横滑りや沈下を防ぎます。地盤が不安定だと沈下や転倒の原因になるため、丁寧な準備が欠かせません。
2. 支柱・枠の組立てと筋交いの取り付け
ジャッキベースに支柱や枠を立て、水平器などを用いて水平を確認した後、隣り合う枠同士に交差筋交い(筋交い)を取り付けて剛性を確保します。くさび式や単管足場の場合は支柱を所定の間隔で立て、緊結金具で接続します。
3. 作業床(布板)の設置
作業床には滑り止め付きの布板(フック付き足場板)を用います。労働安全衛生規則では、作業床の幅を40 cm以上とし、板同士の隙間は3 cm以下、板と支柱の隙間は12 cm未満にしなければならないと規定しています。布板は二つ以上の支点に固定し、脱落しないよう掛け渡します。布板を不規則に並べると耐力が低下するため、隙間なく敷き詰めることが重要です。
4. 手すり・落下防止設備の設置
組み立て作業は手すり先行工法を採用するのが望ましいとされています。この工法は、作業床を設置する前に外側の手すり(親綱や手すり枠)を取り付ける方法で、上部の作業床に昇る際も常に手すりが存在するため墜落リスクを大幅に減らせます。解体時も作業床を撤去するまで手すりを残すので安全です。手すり先行工法には以下の種類があります。
- 先送り方式(手すり送り出し方式) –
下層からスライド式の手すりを送り出して取り付け、上階の作業床を設置する方式。 - 据置き方式 –
手すりを下層から組んで据え置き、上層作業後も最後まで残す方式。 - 専用足場方式 –
手すりや中桟が組み込まれた専用部材を使う方式。簡単に安全性を確保できるため普及しています。
労働安全衛生規則では、高さ2 m以上の作業場所では墜落防止設備を設置する義務があり、手すりや中桟、幅木、メッシュシートなどの組み合わせで落下物対策を行います。幅木等は高さ10 cm以上とし、作業の性質上取り外す場合には立入禁止措置をとることが求められます。
5. 梯子・階段の取り付け
足場内に階段や梯子を設置し、労働者が安全に昇降できるようにします。枠組み足場の場合、階段は2~3スパンごとに設置し、手すりは高さ85 cm以上、中桟は35〜50 cm程度に取り付けます。通行用開口部には安全帯の取付設備を設け、落下防止策を徹底しましょう。
6. 壁つなぎ・控え・防護棚の設置
高さのある足場には建物と足場を連結する壁つなぎや、外側へ倒れないよう支える控えを所定の間隔で設置します。労働安全衛生規則ではわく組足場等における壁つなぎの間隔を垂直方向9 m、水平8 m以下と定めています。高層現場では飛来落下防止のため、朝顔(防護棚)を10 m以上で1層、20 m以上では 2層設置し、張り出しは2 m以上・角度は70°と規定されています。
足場解体のポイント

足場の解体は組立ての逆順で行われますが、準備や安全対策が重要です。以下のポイントを押さえましょう。
1. 事前準備と安全確認
解体前には足場の固定状況を確認し、図面や施工計画に従って作業順序を決めます。フルハーネス・ヘルメット・安全靴などの保護具や必要な工具を用意し、足場の周囲に危険区域を設定して関係者以外の立ち入りを制限します。
2. 解体作業の手順
解体は基本的に上部から下部へと進めます。各段で以下の点に注意します。
- 作業計画に沿って順序良く解体する。無理な撤去や飛ばし作業は禁物。
- 工具の正しい使用 –
ボルトや緊結金具を緩める際にはスパナやハンマーを適切に使い、工具には落下防止コードをつなぎ、落下防止措置を行う。 - 十分な間隔を保つ –
複数人で作業する場合でも適切な距離を保ち、落下物に注意する。 - 周囲を常に確認 –
解体エリアの下部に第三者が立ち入らない事を確認しながら安全に作業する。
大型の足場ではクレーンやフォークリフトを併用する場合もあります。作業主任者は作業全体を監視し、異常があればすぐに作業を止めて安全を確保します。
3. 解体後の片付けと点検
解体した部材は種類別に整理し、欠損や変形がないかを点検してから次回の使用に備えます。作業現場の清掃も忘れずに行いましょう。費用や時間の面では、計画的に作業を進め、効率の良い方法を採用することでコスト削減につながります。
足場に関する法令と資格

使用材料と構造の基準
労働安全衛生規則では足場の使用基準を詳細に定めています。主なポイントは次のとおりです。
- 材料の品質 –
欠損や腐食だけでなく、曲がりなどの変形がある部材や節目・腐朽のある木材を使ってはならないと定めています。材料は定期的に点検し、劣化したものは交換する必要があります。 - 丈夫な構造 –
足場は丈夫な構造でなければ使用できません。 - 本足場の義務 –
2024年の改正で追加された第561条の2では、幅1 m以上確保できる箇所では原則として本足場(両側足場)を使用しなければならないと規定しています。ただし、吊り足場を使用する場合や障害物があり本足場の設置が困難な場合は除外されます。幅が1 m未満の狭い箇所で一側足場を使う場合でも、可能な限り本足場を検討し、手すりや落下防止設備を設けることが求められます。 - 最大積載荷重の設定 –
作業床の最大積載荷重を足場の構造や材料に応じて設定し、それを超えないよう周知する義務があります。 - 作業床の幅・隙間 –
作業床は幅40 cm以上、板間の隙間は3 cm以下、板と支柱の隙間は12 cm未満と規定されています。床材は必ず2 箇所以上の支持点で固定する必要があります。 - 墜落防止設備 –
高さ2 m以上の作業場所では手すりや中桟、幅木などの足場用墜落防止設備を設置し、落下物防止のため幅木等を10 cm以上に設けなければなりません。
組立て・解体作業の安全措置
労働安全衛生規則第564条では、足場の組立て・解体または変更を行う際の安全措置を定めています。具体的には、作業時間や順序を作業者に周知し、立入禁止区域を設定し、悪天候時には作業を中止すること、幅40 cm以上の作業床と墜落制止用器具の取付け設備を設けること、資材の昇降にはワイヤや玉掛け袋を使用することなどが挙げられています。
足場の作業主任者と点検者
足場の組立て・解体・変更など危険を伴う作業には、適切な資格を持った作業主任者の選任が必要です。労働安全衛生法第14条や同規則第565条では、足場作業主任者として足場組立て等作業主任者技能講習を修了した者を指名しなければならないと定めています。この技能講習は一般的な「足場の特別教育」とは異なり、5 mを超える足場や吊り足場、張出し足場などの組立てを監督できる資格です。受講資格は21 歳以上で3 年以上の経験、または関連学科卒業後2 年以上の実務経験などが必要とされています。
作業主任者の業務は、材料や工具の点検、作業手順や作業者の配置決定、墜落制止用器具やヘルメットの着用状況の監視など多岐にわたります。さらに、2024年の法改正により、足場で作業を行う際には事業者が点検者を指名し、その日の作業開始前に墜落防止設備の外れや脱落、床材や緊結部の損傷・緩みなどを点検させることが義務付けられました。強風や大雨、地震後あるいは組立て・解体後には、床材や緊結部、幅木の状態、足場の沈下や筋かいの取付け状態など広範囲な項目を点検し、異常があれば補修しなければなりません。点検結果と点検者氏名は記録し、作業が終了するまで保存する義務もあります。
足場の準備:作業計画と設置届

足場を安全に設置するには、現場に合わせた詳細な作業計画と、法令で定められた届出の手続きが欠かせません。
作業計画の重要性
事前に足場設置計画書や作業計画書を作成し、足場の構造・設置場所・工期・安全対策などを明記します。必要書類を準備し、記載内容が正確かどうか確認することが重要です。こうした計画があれば、作業員全員が段取りを共有でき、安全かつ効率的に施工を進められます。
足場設置届の提出基準
労働安全衛生法第88条および労働安全衛生規則別表第7の12では、高さが10 メートル以上の足場(つり足場や張り出し足場を除く)で、組立てから解体までの期間が60日以上となる場合に、機械等設置届(足場設置届)を提出することが義務付けられています。届出先は工事場所を管轄する労働基準監督署で、作業開始日の30日前までに提出しなければなりません。
届出の準備と流れ
届出の準備としては、前述の足場設置計画書や作業計画書を含む必要書類を用意し、設置場所・期間・安全対策などを正確に記載します。準備が整ったら労働基準監督署へ書類を持参または郵送します。法定条件に該当しない小規模な足場でも、事前に届け出を行うことで監督署からの確認通知が届き、適正な設置を証明できます。一般的には組立て予定日の7日前までに提出するのが望ましいとされています。
設置後は、支柱や横架材の安定性、手すりやネットなどの安全装置、作業環境の安全性を定期的に点検し、設置内容や期間に変更が生じた場合は速やかに変更届を提出します。
労働基準法の労働時間と熱中症対策

足場作業は長時間に及ぶことも多く、適切な休憩や暑熱環境への配慮が欠かせません。
労働時間と休憩
労働基準法第34条第1項では、使用者は労働時間が6時間を超える場合は45分以上の休憩を、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を労働時間の途中に与えなければならないと規定しています。休憩時間は単に作業に従事しない手待ち時間ではなく、労働者が権利として労働から解放され自由に利用できる時間でなければなりません。休憩を細かく分割する場合でも、自由に使える十分な長さを確保し、事実上休憩が制限されないよう注意が必要です。
熱中症対策の義務化
熱中症は建設現場での死亡災害が多く、近年その対策が強化されています。労働安全衛生規則の改正により、令和7年(2025年)6月1日からは、暑熱環境下での作業に対して熱中症対策を講じることが事業者の義務になりました。具体的には、WBGT値28°Cまたは気温31°C以上の環境で1時間以上(または1日4時間を超えて)作業する場合に、
- 作業者自身に熱中症の自覚症状がある場合や他者の異変に気付いた場合に速やかに報告できる体制(連絡先や担当者)を定め、全員に周知すること。
- 熱中症の症状が出た際には、作業から離脱し、身体を冷やし、必要に応じて医師の診察や処置を受けさせる手順や、緊急搬送先の連絡先などを事前に整備し、関係者に周知すること。
これらの措置は作業計画や安全衛生計画に盛り込み、休憩所の設置、WBGT値の測定と管理、こまめな水分・塩分補給の指導などと併せて実施することが望ましいでしょう。また、夏場の暑さ対策には空調服用ファンの選び方も重要です。高出力50V・中出力43V・低出力18Vの空調服ファンを比較したガイドはこちらからご覧いただけます。
よくある質問(Q&A)

Q1. 足場設置届はいつ必要ですか?
A. 労働安全衛生規則別表第7の12では、つり足場や張出し足場を除き、高さ10 m以上の足場を組立て解体までの期間が60日以上にわたって使用する場合に、機械等設置届(足場設置届)の提出が義務付けられています。届出は工事場所を管轄する労働基準監督署へ、作業開始日の30日前までに行います。これより小規模な足場でも、作業計画書や設置計画書を備え、必要に応じて届け出ることで監督署の確認を受け安全性を高められます。
Q2. 足場を組み立てる前にどのような作業計画が必要ですか?
A. 足場を安全に組み立てるには、足場設置計画書や作業計画書を作成し、足場の種類・構造・設置場所、使用期間、作業手順、墜落防止設備や荷重制限などを詳細に定めます。これらの資料は足場設置届の添付書類としても必要であり、関係者全員が共有することで安全かつ効率的な作業が実現します。
Q3. 作業時間中の休憩はどのように取ればよいですか?
A. 労働基準法第34条により、1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与える必要があります。休憩は労働時間の途中で取らせ、労働者が自由に使える時間としなければなりません。夏場の高温環境では、こまめな水分補給や日陰での休息も合わせて実施しましょう。
Q4. 熱中症対策の義務化とは何ですか?
A. 改正労働安全衛生規則により、2025年6月1日から暑熱環境下での作業に熱中症対策を講じることが事業者の義務となりました。WBGT値28°Cまたは気温31°C以上の環境で作業する場合には、熱中症の症状を報告する体制を整え、作業者が異変を感じたら直ちに離脱・冷却・医療機関受診ができる手順を定める必要があります。こうした対策は作業計画と合わせて現場全体で共有しなければなりません。
当社のサービス

藤羽では足場工事だけでなく、さまざまな仮設・施工サービスを提供しています。
- 足場仮設工事 – 鋼管による仮設倉庫の設置や特殊足場工事のご相談を受け付け、現場調査から組み立て・解体まで安全第一で対応します。
- 雷保護設備設置工事 – 高さ20 mを超える建物に義務付けられる避雷針の設置をはじめ、建物を落雷から守るための設計・施工を行います。避雷針の種類や設置基準、施工プロセス(接地極・引き下げ導体・棟上げ導体・突針の設置)について詳しく解説しています。
ニュース・ブログ

藤羽では足場や建設関連の最新情報、法令改正、製品レビューなどをブログとニュースで発信しています。アプリのアップデート情報や話題の商品比較記事も掲載しているので、ぜひご覧ください。
- ニュース一覧 – お知らせや新着ニュース、ブログ、アプリの使い方などの記事をまとめています。
- ASIBA+アップデートのお知らせ – 足場数量・費用計算アプリの最新アップデート内容を紹介し、材料費内訳の改善や見積書・請求書自動生成機能の強化など新機能を詳しく解説しています。
まとめと関連ページのご案内
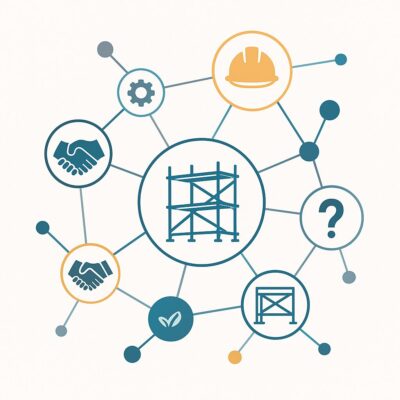
足場仕事は高所作業の安全と効率を支える重要な工程です。現場に合った足場の種類を選び、基礎から手すりまで計画的に組み立て、安全に解体することで事故を防げます。さらに、労働安全衛生規則の改正によって本足場の使用や点検者の指名が義務付けられるなど、法的要求も厳格化されています。適切な材料選び、手すり先行工法の採用、作業主任者・点検者による管理を徹底し、安全な現場づくりを実現しましょう。
おすすめ関連ページ
より詳しく学びたい方は、当サイトの他の記事もぜひご覧ください。以下には計算アプリの使い方や見積もり作成、資格取得、法改正など、現場で役立つ情報へのリンクを整理しました。
- 架け郎(枠組足場版) – 組立パターンや幅を選択し、スパン数を入力するだけで必要部材・重量・費用を自動計算できる枠組足場用ツール。
- 架け郎(くさび足場版) – くさび式・次世代足場に対応し、支柱・手すり・アンチ・ジャッキベースなどを自動で算出する無料ツール。組立パターンと幅を指定するだけで、現場に応じた部材構成が得られます。
- 材料拾いを楽にするアプリの使い方 – スパン数と段数を入力するだけで足場数量が瞬時に分かるため、手作業で1時間かかっていた計算時間をほぼゼロに短縮できます。
- ASIBA+操作説明書 – 次世代足場計算アプリの操作手順をまとめたページ。作業パターンや手すり仕様の選択、自動割付けやオプション部材の設定、Excel/CSV出力方法などを詳しく紹介しています。
- 足場面積の計算方法と価格の相場 – 建物の外周に余裕を加え、手すり高さを考慮して正確に足場面積を算出する方法や単価の目安を紹介し、計算アプリの活用法も解説しています。
- 足場解体の手順と注意点 – シートや安全器具、壁つなぎ、手すり、作業床、筋かい、根がらみの順に解体する手順と、保護具や安全区域の設定などのポイントをまとめています。
- 足場の点検に必要な資格とタイミング – 経験豊富な作業主任者や仮設安全管理者などの資格者が点検を行う必要性と、組立て直後や悪天候後の点検時期について解説しています。
- 足場作業主任者資格講習のポイント – 5 mを超える足場や吊り足場・張出し足場で必要な作業主任者の講習内容や受講資格、講習の流れを説明します。
- 足場使用規制強化の解説 – 改正労働安全衛生規則では幅1 m以上の箇所で本足場の使用を義務付け、作業床と建物の間隔を30 cm以内にするなど安全基準を明確化しています。
- 会社情報 – 当社の会社名・所在地・資本金・事業内容などを掲載したページです。
- 足場仮設工事(サービス紹介) – 仮設倉庫や特殊足場工事について、現場調査から組み立て・解体までの流れを紹介しています。
- 雷保護設備設置工事(サービス紹介) – 建物を落雷から守る避雷針の設置基準や施工プロセスについて解説しています。
- ニュース・ブログ一覧 – 最新ニュースやブログ、アプリの操作方法など多様な記事をまとめたページです。
- ASIBA+アップデートのお知らせ – 材料費内訳の改善、労務費計算の強化、見積書や請求書の自動生成など、アプリの最新機能を紹介します。
これらのリンクを通じて、計算アプリの活用方法から見積書作成、法改正のポイントまで網羅的に学ぶことができます。ぜひ気になる記事をクリックして、当サイト内を回遊しながら理解を深めてください。