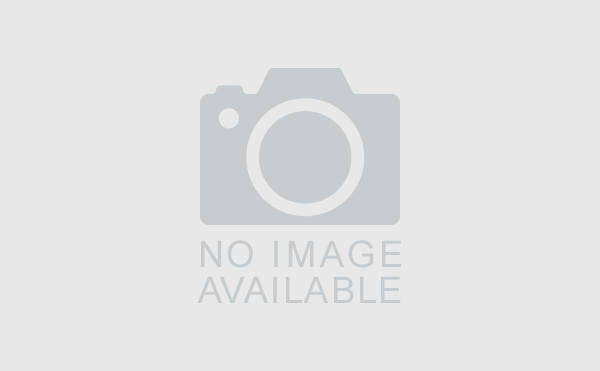住宅・大規模建築の足場計画と法令・資格
このページでは、住宅と大規模建築に分けて足場の種類を解説し、それぞれの組み立て・解体手順や安全対策に加え、足場計画に関する法定事項や必要な資格を網羅的に紹介します。
基本的な足場の種類やメリットについては、「足場とは?種類・特徴・メリットを徹底解説」でも紹介しています。あわせてご覧ください。
1. 住宅向けの足場組み立て・解体
戸建て住宅や小規模リフォームは敷地が狭く工期が短いため、軽量で組み立てやすい足場が選ばれます。安全に作業するためには、足場を組み始める前に地盤や基礎の状態を確認し、作業員には安全帯やヘルメットなどの保護具を着用させることが大切です。
1.1 くさび式(ビケ)足場
- 用途・特徴:戸建て住宅の外壁塗装や屋根工事に適しており、部材をくさびで固定するため設置と撤去が迅速です。高さ2〜3階程度まで対応します。
- 主な部材:支柱、手すり、踏板、ジャッキベースなど。
- 組み立て手順:基礎となる敷板を水平に並べ、ジャッキベースを置きます。支柱を建て、交差筋交いで固定してから布板を敷きます。二層目以降も同じ手順で繰り返し、上層では手すりを先に取り付ける手すり先行工法を採用します。
- 安全対策:基礎が水平であることを確認し、支柱や筋交いの接続部は過不足なく打ち込みます。作業中は墜落制止用器具やヘルメット、滑り止め付き作業靴を着用し、荷物の上げ下ろしは二人以上で行って落下物を防ぎます。
- 解体:組立の逆順で、最上層から手すり → 布板 → 筋交い → 支柱の順に外します。解体中は工具や部材の落下に注意し、解体後は部材の損傷や腐食の有無を確認して保管します。
1.2 単管ブラケット足場
- 用途・特徴:細長い敷地やL字形の建物など、形状が複雑な住宅で使われます。鋼管とクランプを組み合わせるため自由度が高い反面、施工には熟練が必要です。
- 組み立て・解体:支柱を単管パイプで立て、ブラケット(金具)を固定して布板を載せます。高さに応じて筋交いを増やし安定させます。解体時は上部から順に単管パイプやブラケットを外し、部材は一箇所にまとめて整理します。
- 安全対策:クランプの締め付けトルクを均等に保ち、ゆるみがないかを確認します。風の強い日は作業を中止し、最大積載荷重を超えないように材料を配置します。
2. 大規模建築向け足場

高層建築や大規模施設では長期間の使用や強風への耐性が求められます。作業前に施工計画書と設計図を確認し、基礎の水平や壁つなぎの位置、荷重計算を把握する必要があります。安全設備や周囲の状況を十分に確認して作業を進めます。
2.1 枠組み足場
- 用途・特徴:マンションや中層ビルの建築・改修工事で標準的に使用される足場です。ユニット化された部材を組み合わせるため堅牢で、高所作業や長期工期に適します。
- 組み立て手順:敷板を水平に設置してジャッキベースを立てます。建枠を差し込み交差筋交いで固定したら足場の水平を確認し、布板を渡して根がらみパイプで縦枠を安定させます。この段階で親綱を上段に先行張りし、昇降設備(梯子や階段)を設置してから上段の施工に進みます。上段では常に親綱に墜落制止用器具をかけた状態で作業を進めます。
- 安全対策:壁つなぎやアンカーを適切な間隔で設置し、台風時は養生ネットを剥がすなどの対策を行い強風に備えます。作業員は必ず安全帯やフルハーネス型墜落制止用器具を装着し、布板に泥や水が溜まらないよう定期的に清掃します。
- 解体:解体前に区域を立入禁止にし、危険箇所を表示します。最上層から手すり・階段・布板・筋交い・支柱の順で外して下へ進みます。解体後は部材を点検し、錆や損傷があれば交換します。
2.2 単管足場(単管パイプ足場)
- 用途・特徴:工場やプラントの配管周り、複雑な形状の外壁工事などで使用されます。単管パイプとクランプで自由な形状を作れるため、配管や設備を避けながら設置できます。
- 組み立て・解体:支柱を単管パイプで立て、クランプで水平材や筋交いを取り付け、布板や足場板を敷きます。解体は上部から単管パイプ・クランプを順に外します。
- 安全対策:単管同士の接続部を定期的に点検し、錆びや亀裂を早期に発見します。足場を建物に固定する壁つなぎを適切な位置に設けます。
2.3 吊り足場(吊り下げ式足場)
- 用途・特徴:地面に足場を立てられない場所(橋梁の下、吹き抜け、工場の屋内高所など)で使用されます。梁や構造物から吊りチェーンで吊り下げるため、下部にスペースを確保したまま作業できます。
- 組み立て・解体:梁や鉄骨から吊りチェーンや親パイプを取り付け、コロバシを長してその上に足場板を敷いて組み立てます。解体は作業者が順次手すり、足場板、コロバシを取り外し、最後に吊りチェーンから親パイプを抜いてから吊りチェーンを外します。
- 安全対策:吊元の強度計算を行い、吊りチェーンやワイヤーは定格荷重を超えないものを使用します。作業床には安全ネットを張り、作業員は必ず2丁掛けの適正使用で確実に身体を保持します。
2.4 次世代足場
- 用途・特徴:高層ビル、スタジアム、商業施設など大規模な構造物や長期工事で採用される次世代足場です。部材の組み合わせ次第で複雑な形状にも対応できます。
- 組み立て・解体:支柱に水平材の楔を叩いて連結し、上段の筋交いと布材を連結して布板を掛けて上段に進んでいきます。解体は組み立ての逆順で進めます。
- 安全対策:各足場に対して管理者が点検を行い、手すりの脱落や損傷がないか確認します。組立・解体に携わる作業者は研修を受け、現場の安全ルールを遵守します。
2.5 移動式足場(ローリングタワー)
- 用途・特徴:体育館の天井の塗装や電球交換、工場や商業施設の天井作業などで用いられる小規模な移動式足場です。キャスター付きのタワー状足場で、組んだまま移動できるため効率的です。
- 組み立て・解体:基部にアウトリガーやキャスターを取り付け、縦枠と横枠をはめ込みながら塔状に組み上げます。解体は上部から順に部材を取り外し、最後にキャスター部を撤去します。
- 安全対策:作業前に床面の凹凸や傾斜を確認し、キャスターのストッパーを必ずロックします。作業員を乗せたまま移動しないこと、アウトリガーを十分に張り出して転倒を防止することが重要です。
3. 足場計画に関する法定事項
足場の計画・設置にあたっては、労働安全衛生法および労働安全衛生規則などの法律に基づき、以下の点を遵守する必要があります。
- 使用材料:損傷・変形・腐食のある部材や、割れ・虫食いなど強度の欠点がある木材は使用しないことが義務付けられています。
- 作業床の規格:高さ2 m以上の足場では、作業床の幅を40 cm以上、床材間の隙間を3 cm以下、床材と建地の隙間を12 cm未満にする必要があります。床材は転位・脱落しないよう二つ以上の支持物に取り付け、落下物がある恐れがある場合は高さ10 cm以上の幅木やメッシュシートなどを設けます。
- 墜落防止対策:作業床には手すりや中さんを設置し、要求性能墜落制止用器具(フルハーネス等)を安全に取り付ける設備を設け、労働者に使用させます。作業区域への立ち入りは関係者に限定し、悪天候時は作業を中止します。
- 材料の受渡し:足場材の緊結や取り外し、受け渡しを行う際は幅40 cm以上の作業床を設けるか、それが困難な場合はつり綱やつり袋等で材料を上げ下げし、落下を防止します。
- 主任者の選任:事業者は足場の組立て・解体・変更に際し、技能講習を修了した「足場の組立て等作業主任者」を選任しなければなりません。主任者は材料や工具の点検、作業方法と配置の決定、作業の進行監視、安全帯の使用状況確認などを行います。
- 点検の義務:足場作業を開始する前や強風・豪雨・地震後、また組立てや一部解体後には、床材の損傷や緊結部のゆるみ、筋かい・壁つなぎの状態などを点検し、異常があれば直ちに補修します。点検記録は作業が終了するまで保存します。
- 届出義務:つり足場や張出し足場、または高さ10 m以上で使用期間が60日以上の足場を設置する場合は、工事開始の30日前までに所轄の労働基準監督署長へ足場設置届を提出する必要があります。
4. 足場の組み立て・解体に必要な資格
安全に足場作業を行うためには、作業内容に応じた資格や講習を受ける必要があります。主な資格と取得条件を以下にまとめます。
- 足場の組立て等作業主任者技能講習:足場の組立て・解体・変更作業の責任者として作業主任者を選任するための資格です。受講資格は満21歳以上で足場作業に3年以上従事した者、または土木・建築・造船系学科の卒業後に2年以上経験を持つ者などです。講習の標準カリキュラムは学科13時間と修了試験1時間で構成されますが、保有資格や実務経験に応じてBコース(学科3時間+試験1時間)やCコース(学科1.5時間+試験1時間)の短縮講習が用意されています。講習では材料や工具の点検、作業方法の決定、進行監視、安全帯の使用状況の確認などを学びます。
- 足場の組立て等特別教育:主任者以外の作業員が足場の組立て・解体・変更に従事する際に必須となる教育です。カリキュラムは学科6時間(足場の方法3時間・設備0.5時間・労働災害の防止1.5時間・関係法令1時間)で、実技はありません。経験豊富な作業者を対象とした3時間の短縮講習もあります。18歳以上であれば受講でき、足場の種類や組立て方法、墜落防止策を体系的に学びます。
- 玉掛け技能講習/特別教育:クレーンで部材を吊り上げて運搬する場合に求められる資格です。吊り荷重が1 t以上の現場では、18歳以上が対象となり、学科12時間(力学免除者は9時間)と実技7時間、計3日間の玉掛け技能講習を受講して修了試験に合格する必要があります。吊り荷重1 t未満の作業は、学科6時間・実技4時間の玉掛け特別教育(合計10時間)で対応でき、こちらは試験を伴いません。
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育:高さ2 m以上の高所で作業する者は、フルハーネス型墜落制止用器具の正しい装着と使用方法を学ぶ特別教育を受講しなければなりません。一般コースは学科4.5時間・実技1.5時間の合計6時間で、経験者向けには学科4時間程度に短縮したコースや、再教育として約1.5時間の講習もあります。
- その他必要となる資格:現場条件によっては、小型移動式クレーン運転技能講習やフォークリフト運転技能講習などの操作資格も必要になります。小型移動式クレーン運転技能講習は、学科13時間(免除により10時間または7時間)と実技7時間で構成される3日間の講習です。フォークリフト運転技能講習は、所持免許に応じて受講時間が35時間(学科11時間+実技24時間)、31時間(学科7時間+実技24時間)、15時間(学科11時間+実技4時間)、11時間(学科7時間+実技4時間)と分かれており、4〜5日間にわたって行われます。
資格取得機関と受講料
下表では、足場関連の主要な資格を取得できる講習機関と受講時間・受講料の目安をまとめています。講習の内容や受講条件は受講者の保有資格や実務経験によって免除科目が発生する場合があり、費用も変更されることがあります。金額は2025年8月時点で公表されている情報であり、最新の情報は各機関のサイトで確認してください。
| 資格 | 主な講習機関 | 受講時間 | 受講料(例) |
|---|---|---|---|
| 足場の組立て等作業主任者技能講習 | 労働技能講習協会(東京本部)、建設業労働災害防止協会(技術技能講習センター)など | Aコース: 学科13時間・修了試験1時間 Bコース: 学科3時間・修了試験1時間(免除対象者) Cコース: 学科1.5時間・修了試験1時間(免除対象者) | A:14,260円(受講料+テキスト) B:11,100円(受講料+テキスト) C:10,590円(受講料+テキスト) |
| 足場の組立て等特別教育 | 労働技能講習協会、技術技能講習センター、SATなど | 学科6時間(足場の方法3時間・設備30分・災害防止1時間30分・法令1時間)、実技なし。経験者向けには3時間の短縮コースもあります。 | 約9,300〜10,500円(受講料+テキスト) |
| 玉掛け技能講習 | 労働技能講習協会、日本クレーン協会(岐阜支部)、NASUクレーン教習所など | 学科12時間(9時間※力学免除)+実技7時間 | 例: 労働技能講習協会Aコース25,000円、Bコース23,000円。NASUクレーン教習所では資格・経験に応じて22,500〜19,400円程度。 |
| フルハーネス特別教育 | 労働技能講習協会、SAT、建災防など | 一般コース: 学科4.5時間・実技1.5時間(計6時間) 経験者コース: 約5時間 再教育: 約1.5時間 | 例: 一般コース約11,000円、経験者コース9,000円、再教育5,100円 |
| 小型移動式クレーン運転技能講習 | 東京技能講習協会、日本クレーン協会(岐阜支部)、NASUクレーン教習所など | 学科13時間(力学免除で10時間、力学・原動機免除で7時間)+実技7時間 | 例: 東京技能講習協会Aコース33,500円、Bコース30,500円。NASUクレーン教習所では33,000円前後。 |
| フォークリフト運転技能講習 | 東京技能講習協会、各地の安全教育センター、トヨタL&F東京教習所など | 35時間(学科11時間+実技24時間)〈所持免許なし〉 31時間(学科7時間+実技24時間)〈自動車免許保有〉 15時間(学科11時間+実技4時間)〈特別教育修了かつ運転経験6か月以上〉 11時間(学科7時間+実技4時間)〈大特免許保有かつ運転経験3か月以上〉 | 例: 東京技能講習協会では31時間コース41,000円、11時間コース18,500円。トヨタL&F東京教習所では46,750円(学科11h+実技24h)など。 |
各資格には受講年齢や必要な実務経験といった条件があります。受講を検討する際は、講習機関のウェブサイトで最新の日程や申込方法を確認し、受講資格を満たしているかを事前にチェックしてください。
5. まとめ
戸建て住宅では、くさび式や単管ブラケット足場のように軽量で組み立てが容易な足場が用いられます。一方、マンションやビル、工場など大規模建築では枠組み足場や次世代足場、吊り足場など強度と耐久性に優れた足場が主流です。足場計画では法令で定められた幅や隙間、墜落防止設備の設置、主任者の選任、届出義務などを遵守し、日々の点検を欠かさないことが重要です。また、作業内容に応じた資格や講習を受講し、適切な保護具を使用することで安全に作業を進めましょう。
安全に足場を使うための総合的なポイントや資格要件については、「足場仕事とは?安全な足場の重要性・種類・組立て手順・解体のポイントを徹底解説」をご参照ください。また、足場面積の計算方法の詳細は、「足場面積(m2)の正確な計算方法とは?専門家が徹底解説!」で解説されています。